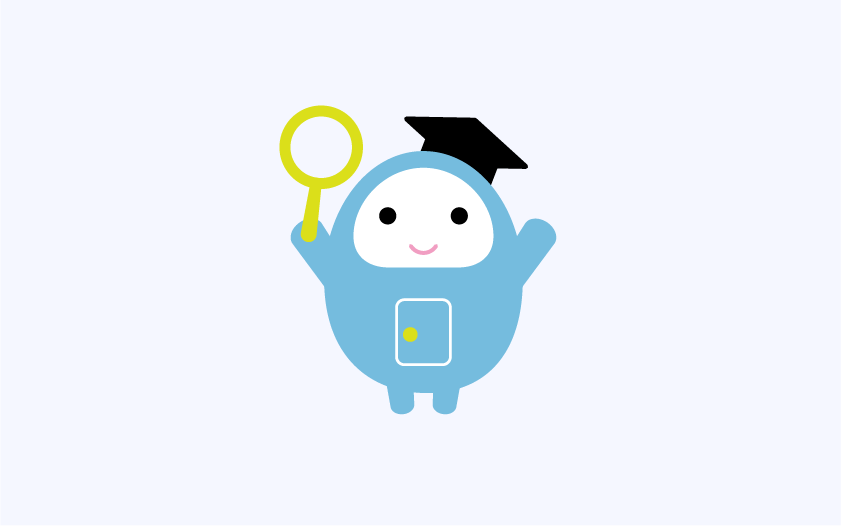鎌倉の子供たちにプログラミング技術を授ける「コンピュータおじちゃん」。教えるのは”コード”ではなく”生み出す楽しさ”。
新宿から電車で約1時間、横浜から約20分の距離にある鎌倉市。神社などの歴史建造物が多く並び文化都市として名を博す一方、七里ヶ浜や稲村ヶ崎、由比ヶ浜など多くの海岸を持つことで「リゾート地」としても有名です。 また、東京や横浜など都心部での目まぐるしい生活に疲れたビジネスマンが週末だけ過ごしたり、セカンドハウスを置いたりという「別荘地」のような側面も持つ鎌倉。 その流れもあってか、昨今、コワーキングスペースが増えたり、IT企業が進出したりと、技術やビジネスの面で俄かに変化が起きています。 「カマクラビットラボ」というプログラミング教室がオープンしたのは、2018年のことでした。リタイア世代が中心となって、現役時代の知識や経験を活かし、小学生を対象にプログラミングを教えるというこの取り組みは、市内外からも評判です。 img_tag_1ビットラボの開催場所は鎌倉駅から5分ほど歩くと現れる荘厳な造りの「結の蔵」。 創設者の山本修さんは、小学生の頃から今まで鎌倉のまちとともに人生を歩みました。しかし東京のメーカーで開発に携わっていたおよそ30年間は、鎌倉が帰って寝るだけの場所になっていたと言います。 現役を退いたいまだからこそ、培った知識や経験を、これから大人になっていく子どもたちに還元したいと思い、ビットラボを開設したそうです。山本さんは「プログラミング」を教える動機や背景について、次のように語ってくれました。 「プログラミングと言うと、カタカタとキーボードを打ってパソコンに向き合う『単純作業』のようなイメージがありますが、実際には論理的思考力や物事の背景を知る力などを鍛えるための手段なんです」 img_tag_2自ら前に立ち、フィジカルコンピューティングについて教える創設者の山本修さん。 img_tag_31回の講義には約10人〜15人の親子が集まる。山本さんの他、数名のメンバーが巡回しながらサポートする。 「ここにこう入力してしまうと、こういう不具合が起きる。そのためにここを改善すると、今度はこんな事象が起きて…。と考えることの連続なんです。課題を設定して、そこに向かって進めていく。つまり、学校のほとんどの教科、いや、それだけでなく生きることの基礎とも言えますね」 「2020年に、小学校でプログラミングが必修化されます。文部科学省の意図としても、ITの開発人口を増やすことへの対応というよりは、生きることへの手段として位置付けています。その証拠に『プログラミング』という授業はなく、理科や数学、音楽、図工など既存の教科の中に埋め込まれるかたちなんです」 ▼ 画面に打ち込むだけが、プログラミングじゃない。実際に「物」を作ることで「生み出す楽しさ」を知る。 img_tag_4 ビットラボで行われるプログラミングというのは、一般的にイメージされるような「画面に向かってコードを打ち込み続ける」というものではなく、実際に手で触れられる「物」を作りそれをプログラムで動かす「フィジカルコンピューティング」と呼ばれる分野です。 例えば、玩具がそのひとつ。「モグラ叩き」など、子供が喜び、かつ一般的に知れたものを成果物とし、トンカチや、モグラの代わりに「ランダムに光るアイコン」などをプログラミングによって作製します。 img_tag_5ビットラボオリジナルのモグラ叩き。「プログラミング」でありながらも、その工程の多くが「工作」となる。 もともとフィジカルコンピューティングが専門だったという山本さんは、その長所や効果について語ってくれました。 「PC上のプログラミングだけだと、画面を見ているだけなのですぐ飽きちゃうし、これテレビゲームでいいじゃんとなる。でもフィジカルだと、実際に手で触れられる『物』ができて、それが動いたり光ったりするのが何より嬉しい」 「『プログラミング』という言葉にアレルギーがあっても、実際その工程は図工に近いので、より親しみやすいんだと思います」 また、カマクラビットラボで広報を務める二藤部知哉さんは、フィジカルコンピューティングだからこそ、作業場に「笑い」が起きると話してくれました。 「画面上のコンピューティングでは作り手一人で完結してしまいますが、フィジカルでは実際に出来上がった物を見せ合ったり、交換したり、意見を言い合ったりできますよね。思わぬ不具合があったり、見た目が面白かったりすると、その場に笑いが起きるんです」 img_tag_6見回りながら、親子のサポートに回るPR担当の二藤部知哉さん。 「こういうことは普通のプログラミング教室のように、一人で黙々とやっていたら起こりづらいですよね。人対人のコミュニケーションもプログラミング作業の一環です」 このように子供が安心して楽しく作業ができるのには、隣に保護者がいるということも関係しているようです。ビットラボでは原則「親子」での参加がルール付けられています。 その理由には、「復習」が関係していました。帰宅後に再び練習しようと思っても、分からないところ、覚えていない箇所があれば先に進むことができず、そのうちに飽きが来てしまうかもしれません。 しかし親が隣についていれば、不明な点を補ってくれることもあり、家でも継続することが可能です。このような考えから、親子での参加が必須とされているんです。 ▼ リタイア組が知識や経験をまちに還元し、受け継いだ子供が社会に活かす。こうした正の循環がベッドタウン鎌倉を支える img_tag_7 多くの工夫により連日大盛況のビットラボ。山本さんは、リタイア後の時間を鎌倉というまちに還元するのは当然の流れだったと語り、その理由を話してくれました。 「鎌倉にはオフィスや大学が少ない。だから学生や働き世代はみんな東京や横浜などの都心部に流れていきます。日中は高齢者や主婦、子供などで溢れ、夜は疲れたサラリーマンが寝に帰る、というような流れになっています。だからこそ、現役時代に外で培った経験や知識を、リタイア後に還元する、というのは自然な流れなんです」 「今度はいまビットラボで学んでいる子供たちが大人になり、都心部に出てその知識を活かす。それをまた鎌倉に還元してもらう。そのような良い循環がどんどん生まれてくればいいと思います」 img_tag_8子供だけでなく、親も一緒に学び、互いに助け合うのが特徴。 いまでこそ、こうした「還元」の場が鎌倉にも徐々に増えてきましたが、まだ数としては全然少ないと言います。そのことから山本さんは、現在ビットラボの前段として、さらに講座を設けています。 休日に開かれるビットラボとは異なり、平日の放課後に小学校低学年を対象にし、「プログラミング」自体に興味をもってもらうためのアフタースクールを開くことで、ビットラボへ繋げるルートを作っているんです。 img_tag_9講義の最初は「プログラミングとは」という根底の説明から入る。また参加者には、女性も多くいる。 さらにビットラボを修了すれば、主に中学生以上を対象に、実験工房「ファブラボ鎌倉」が主催する「プロジェクトラボ」という応用編も準備されているなど、途切れのない育成過程を用意している山本さん。 そんなビットラボには現在6名のスタッフがいて、そのうち2人はリタイア組だと言います。 自らを「コンピュータおじちゃん」と名乗り、小学生たちに「考えることの楽しさ」を教えるチームメンバー。教室には、今日も子供たちの笑い声が響きます。 【取材協力】 カマクラビットラボ 代表/山本 修 同上 PR/二藤部 知哉 【アクセス】 神奈川県鎌倉市扇ケ谷1-10-6 鎌倉駅西口から徒歩5分ほど 著者:清水翔太 2019/6/25 (執筆当時の情報に基づいています) ※本記事はライターの取材および見解に基づくものであり、ハウスコム社の立場、戦略、意見を代表するものではない場合があります。あらかじめご了承ください。