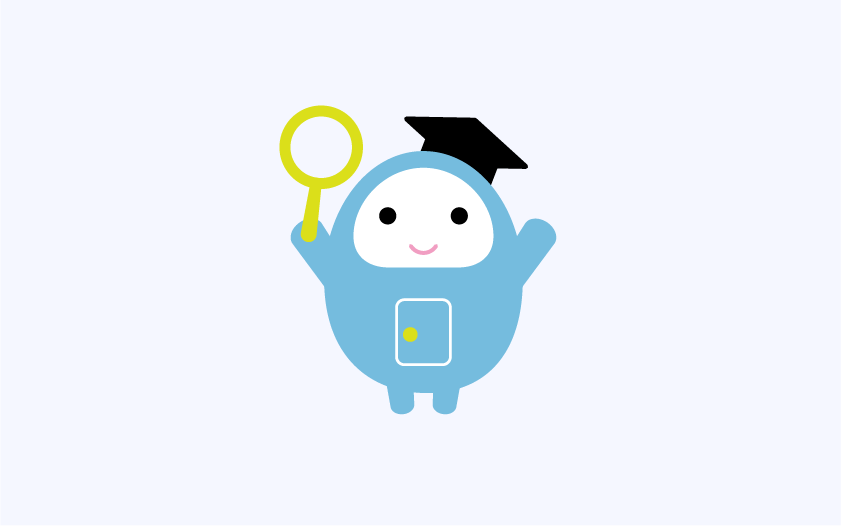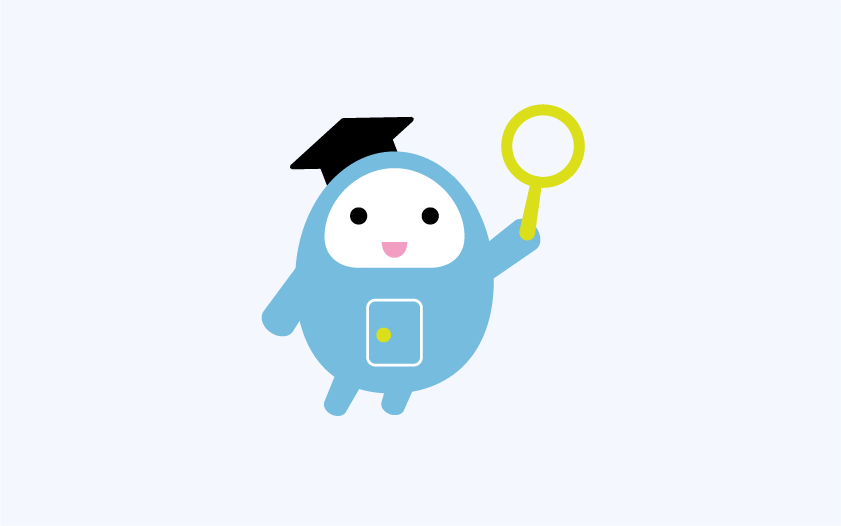変化が著しい時代だからこそ、日常に「何もしない3分」を。谷中の路地裏で商う砂時計専門店、サブリエ・ド・ヴェリエ。
東京都台東区、JR日暮里駅から10分ほど歩くと見えてくる谷中銀座商店街。風情がある、活気がある、といった視点から多くのメディアに取り上げられてきたこの通りですが、一方で、ステンドグラスや手作りランプ、指人形といった風変わりな物を取り扱う店が多いという点でも注目されています。 なかでも話題にのぼっているのが、砂時計専門店。人目を避けるように路地裏にぽつんと佇む「サブリエ・ド・ヴェリエ」という名のその店は、日本に数えるほどしかいない砂時計作家の個性豊かな商品が集まっているということもあり、多くの地元客・観光客が集まる人気スポットとなっています。 img_tag_1谷中銀座商店街の本通りから少し逸れた小道にある「サブリエ・ド・ヴェリエ」。もともと名古屋で砂時計屋を営んでいた和田さんが、およそ7年前この地で開店した。 オーナーの和田朱美さんは、幼い頃から砂時計屋を開くことに憧れがあったと言い、7年前にこの地で夢を叶えました。そんな和田さんが砂時計に惹かれた魅力の一つに、「時間を取り出せる」という不思議な感覚があったそうです。 当然のように、毎秒毎秒過ぎ去っていく時間。時刻、曜日、といった社会的な区切りはありますが、とくに忙しい日々のなかでは、気づかぬうちに夜になっていたというようなことも珍しくありません。 そうしたなか、砂時計を自らの意思でひっくり返すことで、目の前ではじまる「3分」という時間。和田さんいわく、多くの人が「3分て、こんなに長かったんだ」という感想を持つそうです。 当たり前のように流れていく時間が、じつは噛み締めれば貴重なものであること、また時間そのものが流れているという意識を、改めて感じさせる装置なのだといいます。 ▼ 急速に発展する都心部の片隅に流れる、ゆったりとした谷中時間。「このまちは、砂時計そのもの」。 img_tag_2 インターネットの普及により、時間というものがより意識しづらくなっている現代。SNSなどでは昼夜問わず無数の情報が行き交い、スマートフォンやPCを手元に置いている限り、24時間、体がネットに接続されている状態とも言えます。 また、時間の流れに隔たりがなくなってきているのは、まちも同じです。多くの店やビル、駅などでは概ねWiFiが開通しているため、まちそのものがネットのなかにあり、24時間動き続けている世界と接続されています。 とくに東京都心部では、その性質は濃いものと言えますが、一方で台東区谷中のまちは、そうした流れとは無縁かのように、穏やかな日常が広がっています。和田さんは、そのような都心部から分断された感覚が、砂時計専門店を商うのに適していたと、次のように語ってくれました。 「ここは時間が止まったまちなんです。都市開発があまりされてないので、江戸時代からの道が普通に残っていたりする。まさに砂時計のように、大きな時間の流れから、この場所だけが取り出されているんです」 img_tag_3オーナーの和田朱美さん。砂時計の最大の魅力について「時を見つめて、時を忘れられるとこと」だと語る。 「まちの進化は、時間の流れそのものです。例えば渋谷のまちは、いま建設ラッシュで、高層ビルがどんどん建って近未来都市のようになっています。そういう風な発展もいいですが、ちょっと疲れたなって人には、谷中のように時間の止まったまちは癒しな存在なんです」 「とくにこの店は、谷中銀座商店街のなかでもかなり路地裏にあります。車は入れないし、人通りも少ない。時間の流れから逸れた異世界。まさに砂時計そのものです」 img_tag_4店内の壁面を満たすさまざまな種類の砂時計。夜光性のものや、楽器のように音が鳴るものまで幅広くある。オーダーメイド商品も多いという。 そんな谷中に根付いて7年、多くのお客さんが訪れるようになった同店。砂時計というニッチな商品であるだけに、客層も偏っているのかと思われますが、老若男女、多くのお客さんが訪れると言います。 あるときは、夜の仕事をしている人が接客の時間を測るために光る砂時計を使ったり、心理カウンセラーが面談中に時間を測るように使ったりと、砂時計には「癒し」の機能があるぶん、そのようなリラックスが求められる場所では、とくに重宝されているようです。 またここ最近では大人だけでなく、近所の子供たちが、自由研究のために砂時計の作り方を教えてほしいと、訪れることもあるのだそう。和田さんはその度に、ペットボトルと硬貨を使った簡易な作り方を提供しているといいます。 ▼ ゆかりある土地の砂を持ち帰り、オリジナルの砂時計に。「思い出が、いつまでも時を刻み続ける」。 img_tag_5 時間を測るという限定的な機能でありながらも、使い道が多岐に渡る砂時計。さらに、そうした多様な側面を引き出すのは、ほとんどがお客さんなのだそうです。 その代表的なものが、思い入れのある土地の砂を持って帰り、瓶に詰めて自分だけの砂時計をつくるというもの。 img_tag_6 エジプト旅行に行った際に「これを思い出に残したい」と、お客さんがすくってきた砂。その後は、瓶の中に入れてオーダーメイドの砂時計を作るのだという。 新婚旅行先の砂、故郷の砂、そういった思い出深い土地の砂を「自分だけの時間」として手元に置いておきたいという人が多いそうで、現在のオーダーメイド注文の大きなウェイトを占めているといいます。この傾向について、和田さんは以下のように語ってくれました。 「例えば甲子園球児が負けたときにグラウンドの砂を持ち帰るという儀式があるように、『砂』というのは昔から特別なものとして扱われてきました。自分の足で踏んだ土地、という点に大きな意味があるようで、いまでも思い出と密接に関わる存在なんです」 「最近では、結婚式にも使われたりします。参加者一人一人に配られた小瓶の砂を、それぞれが新郎新婦の持つ大きな砂時計に入れていく。全て入れ終わったところで、新郎から『みなさんのお力でぼくたち二人の時間が始まりました』と挨拶があって宴が始まる、という風に」 img_tag_7結婚式で実際に使われる小瓶。青色の砂が男性、桃色が女性の参加者なのだそう。 「このように砂時計というのは、人生の節目、大事なところに関わっていく。人々の『想い』が込めやすいアイテムなんです」 販売店でありながら、カフェとしての営業もしているサブリエ・ド・ヴェリエ。商品を買わうことなく、カウンターでコーヒーを飲みながら、ただ瓶のなかを砂が落ちてくのを見て帰っていくお客さんも多くいるといいます。和田さんとしては、どのようなかたちであれ、「癒し」を提供できればそれで十分なのだそうです。 img_tag_8 フランスの片田舎にあるガラス工房のような佇まいのサブリエ・ド・ヴェリエ。店名は日本語で「砂時計のガラス職人」を意味します。 陽が出てから働きに出、陽が落ちたら帰る、という生活をしていた時代に、「時間」という概念をもたらした砂時計。静かにゆっくりと動くそれは、その後に機械式時計が発明されるまで、世界の時間を優しく支えてきました。 そんな砂時計のように、いまもなお世界の急速な進化とは一線を引き、のんびりとした空気が流れる谷中のまち。穏やかな商店街の路地裏で、一度「時間」というものを見つめ直してみるのもいいかもしれません。 【取材協力】 サブリエ・ド・ヴェリエ/オーナー 和田 朱美さん 【アクセス】 東京都台東区谷中3-9-18 JR日暮里駅から徒歩10分ほど 著者:清水翔太 2020/5/7 (執筆当時の情報に基づいています) ※本記事はライターの取材および見解に基づくものであり、ハウスコム社の立場、戦略、意見を代表するものではない場合があります。あらかじめご了承ください。