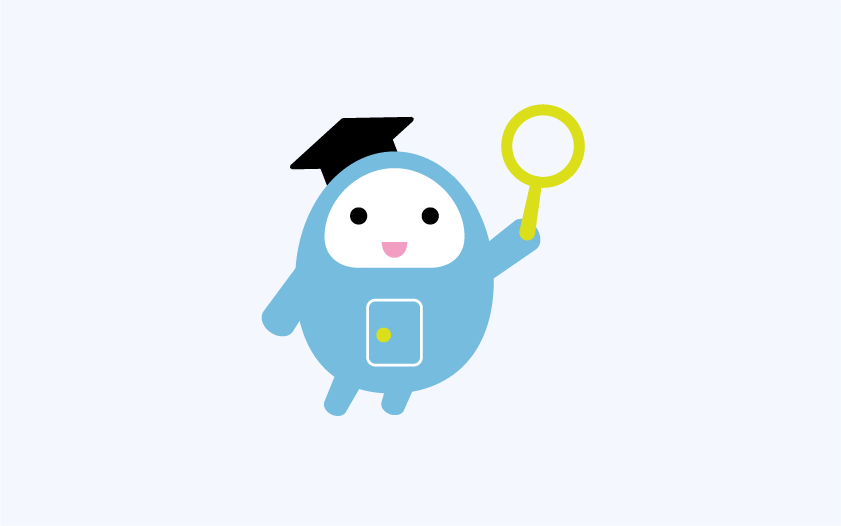
返却期限がない、中野区南台のおうち図書館「本は人から人へ、旅立つものだと思うんです」
1999年に2万店舗ほどあったと言われる書店は、この20年間で約1万2000店舗にまで減りました。 一方で、1店舗当たりの売り場面積は伸びていることから、書店の大型化・集約化の傾向が見られます。 img_tag_1 つまり、姿を消している店舗の多くは、自分が暮らしている町にあるような小さな書店だということですが、そうした状況に対して、カフェや飲食店、民家の片隅のスペースに本棚を設置し、本と触れることができる場所を増やす、「マイクロライブラリー」と呼ばれる取り組みが広がっています。 日曜日の午後になるとオープンし、地域の子どもたちが集う中野区南台のおうち図書館、「友栄文庫(ともえぶんこ)」もその一つです。 管理人の堤香代子さんは、空き家になった古民家でマイクロライブラリーを始めたきっかけを、次のように教えてくださいました。 img_tag_2 img_tag_3 「学生の頃、ホームステイ先のママに教えてもらった本が、今では私のバイブルとなっているんです。本当に良い本だったので、今度はその本を友達に貸したり、おすすめしまくっていました」 「そしたら、その中の一人がすごく本のことを気に入ってくれて、今でもずっと交友関係が続いているんですよ」 「本を通して人と出会える。この場所をきっかけにして、そういう出会いがたくさん起きれば良いなって思ったんです」 そのために堤さんが考えたのが、貸し出す本に返却期限を定めないということでした。そのアイデアの背景には、世界で2万箇所にまで広がりつつある、リトル・フリー・ライブラリーという取り組みの存在があります。 ▼ 返却しなくても良い代わりに、他の誰かに貸してあげて欲しい。「本を手渡す時には、必ず対面でのコミュニケーションが生まれる」 img_tag_4 リトル・フリー・ライブラリーとは、巣箱型の本箱を軒先において図書館にしていく取り組みで、誰でも自由に本を置くことができ、自由に本を持っていくことができる、近くに暮らす住民の手によって中身が変わる、町の小さい図書ポストのようなものです。 好きな本を自由に持って帰ることができるというアイデアが興味深い一方で、返却期限を決めないと本の管理が難しいように思えますが、そのことに関して堤さんは次のように語ります。 img_tag_5 「返却期限もないですけど、極端なことを言えば、この場所に置いてある本は、そのまま持って行ってもらっても構わないと思っているんです」 「その代わりに、借りた人はまた別の人にその本を貸してほしい。そしたら本は、人の手から人の手へと旅をしていることになりますよね」 「本っていうのは旅をするものだと考えているんです。バックパッカーが旅先でお互いが持っている本を交換する、ああいう文化がすごく好きでした」 「いつかちゃんと本が帰ってくるかは、正直分かりません。それに、勝手に本棚から抜き取られることだって考えられます。でも本が帰ってこなくても、きっと誰かの手に渡って、大事にされているんだろうなって思うようにしているんです」 img_tag_6 本が人から人に手渡されるときは、必ず対面でのコミュニケーションが生まれることに加え、同じ本を読むと、考え方を共有したり、その内容について話し合うことができるため、今までお互いに詳しく知らなかった人同士でも、新しい関係を築けるきっかけになると堤さんは語ります。 実際に、フランスのブルターニュ半島という場所では、1974年にテレビ塔が過激派によって破壊され1年間テレビが見れなくなってしまったことがあったそうですが、その時には村の人々がみんな本を読むようになり、コミュニケーションが増えて、人との繋がりが親密になったのだそうです。 本を得る手段が便利なものに画一化し始めている現在、誰かに本をオススメしてもらったり、逆に誰かに紹介することは、時間がかかる半合理的なものかもしれません。 しかし、そこで生まれる人と人の繋がりは、オンライン上でワンクリックで本を買ったり、大型書店で本を買う、という本との出会い方では得ることができないものなのでしょう。 ▼ 小さな図書館の役割は、地域の人が持っている本を循環させること img_tag_7 本の貸し出しを行う図書館は、敷地面積が広く、所蔵されている本の数も多ければ多いほど一般的には良いとされますが、マイクロライブラリーである友栄文庫は、地域で暮らす人がもともと持っている本を循環させる場として機能している点が特徴的です。 というのも、貸し出しのために並べられている本の多くが、地域住民や、堤さんの友人からの寄付によって集められたものなのです。 img_tag_8 本が集まるようになった経緯に関して、堤さんは次のように語ります。 「最初から完璧な状態で始めなかったことが、結果的には良かったのかもしれないです」 「もともとは、人が来てくれるように自分で本をたくさん準備して、家もリフォームしないと始められないんじゃないかって考えていました。でも、『家の前に本を並べて看板を出せば、それだけで図書館になるんじゃない?』って母親に言ってもらえて、それならすぐに始められるじゃんって気が付いたんです」 そうして、手持ちの本だけで始まった友栄文庫。初めは一人で待ちぼうけすることも沢山ありつつも、半年くらい続けると近所の方に認知してもらえるようになり、来てくれるお客さんも、寄付してもらえる本も、徐々に増えていったのだそうです。 img_tag_9 寄付してもらった本が、他の地域住民の手に渡っていく。その中継地点になりつつある友栄文庫について、堤さんは最後にこのように語ります。 「古民家の『古』には、古いっていう意味がありますけど、この場所はコワーキングスペースとかで使われる『Co』の意味での『Co 民家図書館』。つまり、みんなが集まる家みたいな場所に、本を通してこの場所がなっていったら良いかなって思います」 もちろん、本の数も面積も限られてはいますが、軒先の小さな本棚から始まった堤さんの図書館は、地域の方々の手によってだんだんと大きくなり始めているようです。 【取材協力】 友栄文庫オーナー 堤香代子さん 著者:早川直輝 2019/7/16 (執筆当時の情報に基づいています) ※本記事はライターの取材および見解に基づくものであり、ハウスコム社の立場、戦略、意見を代表するものではない場合があります。あらかじめご了承ください。









