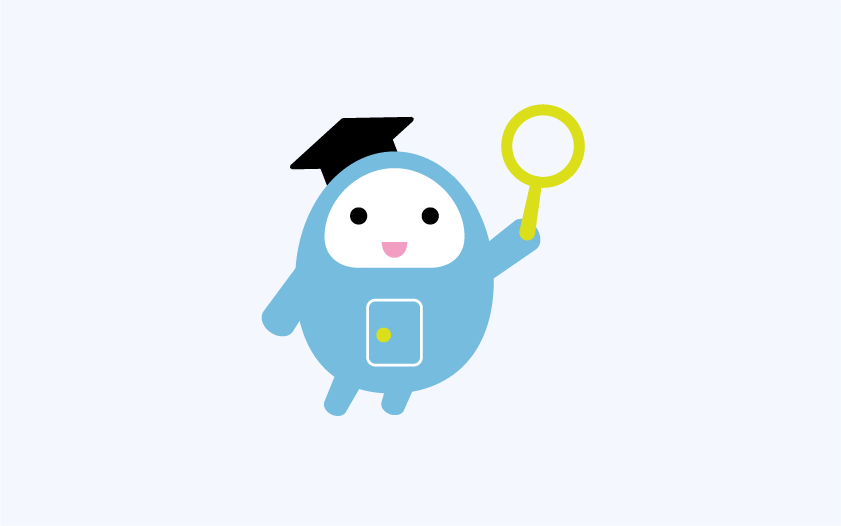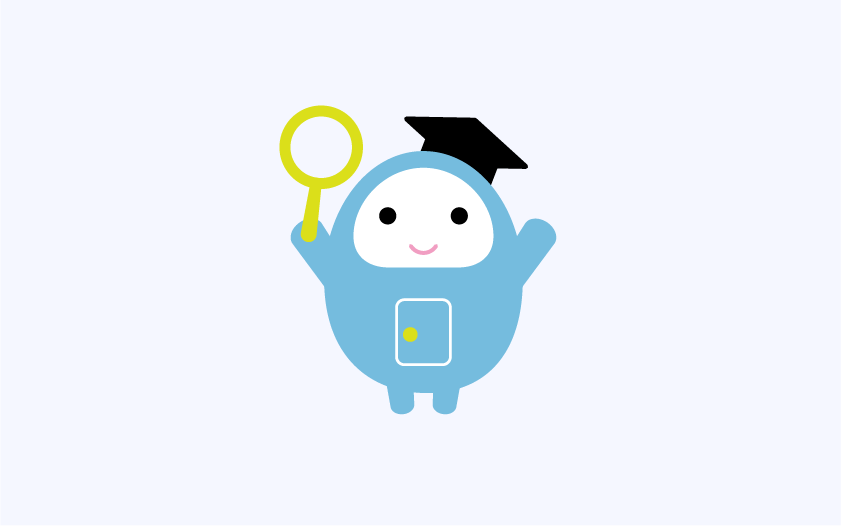 2
2イギリスで、年間利用者数 約29万人。乳がんを経験した一人の女性の想いから生まれた “第二の我が家” とは?
築地から移転した豊洲市場、さらにオリンピック会場となっている有明アリーナも程近い、豊洲の街。 オリンピックを前に盛り上がるこの街で今回訪ねたのは「マギーズ東京」です。 大きな窓ガラスからは、大きなテーブルを囲んで、お茶を飲んだり話したりしている様子が見えます。 ▼ 近くに来た人が「喫茶店かな?」と入ってくる img_tag_1 「この木のテーブルは樹齢300年。材木屋さんが寄贈してくださったんですよ」 そう穏やかに話しながら案内してくださったのは、「マギーズ東京」センター長・共同代表理事の秋山正子(あきやま まさこ)さんです。 秋山さんは次のように続けます。 「近くに劇場があるんですね。通りがかりにこのテーブルでみんながお茶飲んで談笑してたりするのを見た人は、『喫茶店かな?』と思って入っていらっしゃいます。深刻な相談をしていい場所とはとても思わない。」 img_tag_2 実は「マギーズ東京」は、2016年にオープンしたキャンサー ケアリング センターです。 「マギーズ東京」のある豊洲は、がん治療の最先端をいく「がん研有明病院」と「国立がん研究センター中央病院」のほぼ中間地点に位置しています。 さらには「聖路加国際病院」「虎の門病院」「東京慈恵会医科大学病院」といった周辺の大きな病院からもアクセスがいいのです。 img_tag_3晴海運河の対岸には大きなビルも臨める豊洲の街。 マギーズセンターはその名に見られるように、もともとはイギリスで、マギー・K・ジェンクスさんという一人の乳がん経験者の想いで生まれた施設です。 日本の病院でよく言われる“3分診療”のように、イギリスでも患者一人当たりの診療時間が短いことを示す“7分診療”という言い回しがあります。 病院で「余命3ヶ月」という診断を受けたマギーさんも、医師からこう言われたそうです。 「すみませんが、廊下の方に移動していただいてもいいですか?多くの患者が待っているので」 img_tag_4マギーズ東京にあるマギーさんの写真。本当に欲しいのは自分を取り戻せる空間だと、マギーズセンターの開設へ動き出した。 自らの体験から、がんの影響を受けた人が安心して話ができる“第二の我が家”をつくろう、と動き出したマギーさんですが、マギーズセンターの完成を目前に亡くなってしまいました。 しかし、第一号のマギーズセンターがオープンしてからこの25年ほどの間に、マギーズセンターはイギリスのそれぞれの地域で大きな病院敷地内に建設されて20箇所以上に増え、昨年の利用者数は延べ29万人以上にもなったということです。 ▼ 予約不要。本人の来たいタイミングで「モヤモヤした気持ちのまま、お越しください」 img_tag_53.5mもある割れ目の入っていない一枚板のテーブルを囲む。ランプシェードは和紙でつくられている。有名な建築事務所、柳宗理事務所からの寄贈品。 豊洲の「マギーズ東京」は、日本で初めて建設されたマギーズセンターです。 日本でも昔と比べると、がんの影響を受けた人々のための相談窓口は地域や病院などにもありますが、秋山さんはそうした相談窓口とマギーズとの違いについて、次のようにいいました。 「多くの相談支援の窓口は、予約しなければいけません。しかも、ある程度問題が見えていて『これについて聞きたい』と話しておかないと対応してもらえないということがあります。」 「けれど多くの人は、何をどうしたらいいのかがわからない。何を話したいかも決まってなくて、気持ちの中にモヤモヤしたものがある。マギーズの場合、その状態でもどうぞと言っています。予約もいりません。」 img_tag_6お茶を飲みながら、訪れた人が話し出すのを待つ。根掘り葉掘り質問して、何か答えを出す相談の場ではない ということは、マギーズセンターでは初めてマギーズにいらした方の事前情報が何もないことになるわけですが、スタッフのみなさんは訪れた方にどのように応対しているのでしょう? 秋山さんからの答えは、次のようなものでした。 「『どこでもどうぞ』とお茶を勧めながら、ご本人が話したくなるまで待つ。『お名前は?』とか『何のがんですか?』とか、そういう質問はほぼしないですね。」 病院での“患者”と“医者”の関係性においては、人々は“患者”という役割をまとい、医者が伝えたいことを聞く側の立場に徹してしまいがちです。 “第二の我が家”のようなマギーズでは、スタッフは名札をつけていなく、来訪者も名のる必要もなく、家のようにくつろげる状況の中で、人は自ら話出し、「自分で決めていこうとする」のだそうです。 ▼ “肯定も否定もしない”マギーズセンターが、がん患者と病院とのよい関係づくりに役立っている img_tag_7 イギリス20箇所以上と、香港、スペイン、日本にも拠点のあるマギーズセンター。その建設は世界で進んでいます。 イギリスでは、マギーズセンターという“対話”の場が広まったことによって、がん患者から医療機関へのクレームが減ったという報告も上がっています。 それは日本の「マギーズ東京」でも同様で、それまでは医師への応答がぼんやりとしていた人がマギーズを訪れた後の診療では、とてもはっきりと受け答えができるようになった方もおられるそうです。 それによって治療にあたる医療者側も助かっているという場面が増えてきているそうです。 img_tag_8造園家でもあったマギーさんが大切にしていた、大きな窓から見える庭の緑。椅子に座り、窓の外を眺めると自然と気力が湧いてくるのは、マギーズセンターに共通する環境の力。 マギーズセンターで来訪者を迎えるスタッフは看護師、保健師、心理士、栄養士といった医療専門職です。 そういうスタッフたちが医療施設ではないこの場所で「何もしない」ことが大事なのだとして秋山さんは次のように言いました。 「病院の中の医療者は『こうしなさい、ああしなさい』『こうしたほうがいいですよ』って、つい指示や指導をしてしまいがち。でもここでは指示しない。」 「がんで外来にかかった人は、言おう言おうと思いながら言い淀んでいるうちに時間が来てしまって外に出ざるを得ない。家族のこと、お金のこと、仕事のこと、とか。こんなことはお医者さんに聞けない…。」 「そういう人がここに来て、自ら話をし出し、わからないことはきちんと聞こうと決める。次の診療で『短い時間にこれだけは聞こう。ちゃんとフォーカスして聞こう』と。“患者力”が上がるんですよ。」 ▼ 最近のがんの人は「とても忙しい」。それでも自分の人生を手放さないために… img_tag_9 10年20年前を振り返れば、“不治の病”の代名詞として恐れられていたがんですが、早期発見をはじめとする医療の目覚ましい発達によって、発症から5年、10年とつきあっていくような病気に変わりました。 治療も外来治療が主になり、入院でさえ1週間程度だったりしますから、「ちょっと旅行に行ってきます」と会社に隠して治療をする人もいます。 治療が一段落しているがんの人を“サバイバー”とも言いますが、昨今ではがんと共生する時間が長くなっているために、早期発見・早期治療は言い換えれば、“長期不安”なのだそうです。 秋山さんは、近年がんの人は「とても忙しい」として、次のようにお話してくれました。 「ここに来られる方の35%をがんの治療が一段落した人が占めています。彼らはがんが再発するんじゃないかという不安をずっと抱えている。咳が出たら『肺に転移したんじゃないか』、ちょっと痛みが走ると『骨に転移したんじゃないか』とか、ちょっとした体の不調を全部がんと結びつけてしまう。」 「しかも、周りに迷惑をかけるからと、がんになったことは言わない。手術も傷が大きくなく済んでしまったりするので、がんになったことを隠せる時代になっています。」 「でもがんの治療は決して軽い治療ではないんです。薬の影響で指先が痺れるので、今までやって来た仕事はできにくいかもしれない。でも、この仕事のこの部分なら、自分らしさを発揮して続けられるのではないか。そういう気持ちをどう表現するか、仕事先でどう交渉するか、そういったこともここで一緒に考えています。」 「2人に1人ががんになる」という今の時代、薬の影響で子どもが持てなくなるかもしれない、仕事を変えなければならなくなるかもしれないと、何か心に重いものを抱えるようにして生きているがんの人々が、きっと私たちの周りにもたくさんいます。 「マギーズ東京」に訪れる方の中には、入り口の扉を開けた瞬間、涙が溢れ出す人もいるそうです。 豊洲の街で、はじめは“離れ小島”のようにして始まったという「マギーズ東京」。 最近では、チラシを置かせてもらった豊洲の商店街で、お店の人から紹介された人が自転車で相談に訪れるようになっているそうです。 豊洲のある江東区は、江東区在勤/在住あるいは、江東区の病院にかかっている方が相談に来られるようにと夜間相談窓口の委託事業として、月に1度「ナイトマギーズ」という名前でオープンしています。 img_tag_10「マギーズ東京」センター長・認定NPO法人マギーズ東京共同代表理事の秋山正子さん「がんになった人の3割が慌てて仕事を辞めてしまう “びっくり退職” をしていると言われています。仕事に関する相談も多く寄せられています。」 「来よう来ようと思っていたけど、なかなか勇気が出なくて来れなかった。今日は朝から気持ちを奮い立たせながらここにやってきて…やっとドアを開けられた」 マギーズに訪れた方が言うように、がんになるということは新しい人生の入り口に立つということなのかもしれません。 急速に進歩しているがん治療では、診断されたその日に治療計画が出されるまでになっており、がんの人が自分のこれからを自分で考えるゆとりを持つことは、ますます難しくなっています。 それでも、豊洲の「マギーズ東京」のように、がんと共に歩んでくれる人のいる空間が地域にあったなら、がんになっても自分で人生のハンドルをしっかり握り、自分らしく暮らしていけるのではないでしょうか。 ⬛︎取材協力 「マギーズ東京」センター長 秋山正子さん 「マギーズ東京」は、ゆりかもめ「市場前」駅で下車 徒歩3分 著者:関希実子・高橋将人 2020/3/12 (執筆当時の情報に基づいています) ※本記事はライターの取材および見解に基づくものであり、ハウスコム社の立場、戦略、意見を代表するものではない場合があります。あらかじめご了承ください。