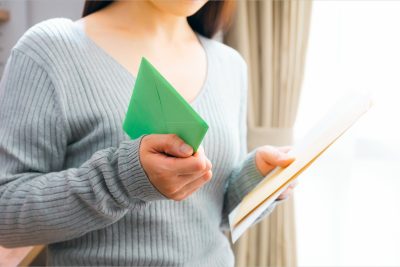終活という言葉が一般的になり、老後のことや自分が亡くなってからのことを気にする機会も増えたのではないでしょうか。
生前の終活は周りの人たちにもさまざまなメリットがあるだけでなく、社会的な課題解決にも繋がる重要なアクションです。そのため、早いうちから取り組むことで自分だけでなくご家族も安心して老後を迎えることができるでしょう。
終活のなかで最近話題になっているのは「墓じまい」。皆さんは詳しい内容までご存じでしょうか。
・墓じまいという言葉の意味がわからない
・お墓がどこにあるのか知らない
・お墓を誰が管理しているのかわからない
今回は、「墓じまい」について手順や費用相場などを解説します。一つ一つ丁寧に解説いたしますので、ぜひ最後までお読みください。
墓じまいとは?
墓じまいとは、先祖代々のお墓を別の場所に移すことをいい、改葬とも呼ばれます。
令和4年度の統計によれば、151,076件の墓じまい(改葬)がされています。この墓じまい件数、実は令和3年度の統計では118,975件と、1年間で1.5倍の件数になっています。
※参考:厚生労働省 「衛生行政報告例」令和3年度衛生行政報告例 統計表 年度報および、令和4年度衛生行政報告例 統計表 年度報
なぜ、わざわざ墓じまいをする必要があり、またその件数が増加しているのでしょうか。これより、墓じまいをする必要性に迫ります。
子どもがいないから
少子高齢化や未婚者の増加が墓じまいを加速させています。なぜなら、お墓は定期的にお参りするのみならず、維持管理が必要だからです。
子どもがいないと墓の維持管理ができなくなるため、墓じまいをする人が増えると予想されます。
お墓参りやお墓の管理が困難な状況だから
昔は生まれ育った街で一生を終えることが一般的でしたが、現在ではライフイベントや異動などを理由として知らない土地で生活することは珍しくありません。そのため、お墓への距離が遠くなることでお墓参りができなくなったり、お墓の維持管理が難しくなったりするため、墓じまいを検討する人が多くなるのです。
経済的に負担がかかるから
お墓の維持管理にはお金がかかりますので、維持管理費用の負担が困難になるため墓じまいを考える人がいます。
お寺や霊園に支払う管理料は年間で20,000円前後が必要です。さらに、墓石のメンテナンス・墓参りの費用・お寺に払う寄付やお布施など、さまざまな費用がかかります。経済的な理由による墓じまいも昨今では珍しくありません。
墓じまいを進める方法・手順

実際に墓じまいを進めるためには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。これより、詳細に解説します。
①墓じまいをするかどうかを決める
最初に取り組むべきは、墓じまいについて親族など関係者と話し合いの場をもつことです。なぜなら、墓じまいは自分だけの問題ではないからです。
お墓に近い人からすれば、墓じまいにより墓参りが面倒になるため反対されることもあるでしょう。お墓を管理する人からすれば、維持管理費を下げたり、近くにお墓を移したいと考えたりして当然です。
そのため、まずはお墓と関係する人たちと話し合いを行い、墓じまいについて意見交換を行うことが重要です。墓じまいに向けた話し合いでは、以下のことを協議しましょう。
墓じまいをしたい理由
墓じまいをする必要性や理由を明確にしておきましょう。経済的な理由・維持管理の難易度・立地の問題など、自分の状況と将来のことを見据え、建設的な議論ができるように準備しておきたいところです。
墓じまい後の供養をどうするか
墓じまいをしてから、どのように供養をするかも考える必要があります。現在では供養の方法も多様に存在しています。墓じまいをしたい理由に合わせ、具体的なプランがあると良いため、ホームページやパンフレットの情報を提供すると説明がスムーズです。
費用負担をどうするか
墓じまいには費用がかかります。そのため、費用面の算出や誰がどのくらい負担するかについても事前に決めておくことが重要です。希望する墓じまいに必要な見積は欠かせません。
事前の予想よりも高額になることもあるため、必要に応じて複数の業者や墓地などから見積を取得するとよいでしょう。
そのほか、墓じまいに補助金が出る自治体もあります。決して数は多くありませんが、一度墓地のある自治体に確認することをおすすめします。
スケジュールをどうするか
墓じまいに際し、新しいお墓の納骨式に参列したいと考える人も少なくありません。そのため、スケジュールについても関係者の希望を聞いておくとよいでしょう。
②お墓の管理者へ報告・相談する
墓じまいについて関係者の意見がまとまったら、お墓の管理者に対して墓じまいをする旨を伝えます。墓じまいは墓地の管理者の許可なく進めることはできません。そのため、早いうちに連絡を入れておくのがよいでしょう。
なお、お墓の管理者がわからないときは、自治体に確認してみてください。お墓は墓地埋葬法に基づき厳格に管理されているため、墓地台帳を確認すればお墓の管理者を特定することが可能です。
③遺骨をどこに移すかを決める
墓じまいしてからの遺骨の移設先を決定します。
なお、遺骨の移設先はお墓以外にもたくさんの選択肢があります。墓じまいの目的や故人の希望などに応じて決定するのがよいでしょう。
④墓石を撤去する
移設先が決まれば、今のお墓をお返しする段取りに入ります。この段階ですべきことは、おもに以下の3点です。
・石材業者選び
・遺骨の取り出し
・墓石の撤去など原状回復
石材業者は墓地によって指定されていることもあるため、管理者へ確認しておきましょう。自由に選べるときは、複数の業者から見積をとると安い業者を選ぶことができるため、余裕があるときは取り組みたいところです。
⑤遺骨を移設する
専門業者に依頼し、遺骨を新しい納骨先へ移します。
新しい納骨先では、納骨式を行うことをおすすめします。なぜなら、今後の供養について決意を新たにする良い機会となるからです。
これら一連の流れが「墓じまい」と呼ばれるものです。終活では、自分の希望や情報を残すことも重要ですが、墓じまいのように重大な選択をする場面に遭遇することも珍しくありません。
墓じまいと一緒に行いたいこととして「家じまい」という言葉があります。家じまいとは文字通り自分の住んでいる家を処分してしまうことです。
墓じまいと家じまいは同じタイミングで行うことをおすすめします。なぜなら、住む場所が変わることで、墓参りに赴く場所や頻度にも影響を与えるからです。家じまいに参考となるサービスや、老後の生活に役立つ設備のある賃貸物件を合わせて検討してみてはいかがでしょうか。
墓じまいにかかる費用

墓じまいの流れを理解できたところで、気になるのは費用のところではないでしょうか。ここでは、まず墓じまいにかかる費用を解説します。
なお、墓じまいにかかる費用は墓地の規模・遺骨の数により大きく異なるため、あくまでも目安としてお役立てください。
お墓の撤去にかかる費用
お墓の撤去(原状回復まで含む)にかかる費用の目安は約20万円程度です。ただし、墓石の大きさや重機が入るかどうかなど、さまざまな要素により変わりますので注意しましょう。
お布施代
墓地の管理がお寺のときなどは、今までの管理に対する感謝の気持ちとしてお布施を支払うことが必要です。お布施は寺院の格によって異なりますが、一般的には5万円程度が相場です。
離檀料
離檀料とは、檀家(お寺を経済的に助ける人)を抜けるときに菩提寺(お墓があるお寺のこと)に支払うお金のことで、一般的には10万円程度が相場です。
なお、お布施代や離檀料は明確に規定がないことがほとんどです。まずは墓地使用契約書に定めがないかを確認し、定めがないときは事前に確認しておいてください。また、離檀料やお布施をめぐるトラブルは決して少なくないため、専門家と相談のうえ進めるのがよいでしょう。
行政に支払う費用
お墓を移動するときには、行政への許可申請が必要です。そのとき、埋蔵証明書・受入証明書・改葬許可書などの書類が求められますので、これら書類の取得費用がかかります。
おおむね1通あたり300円程度ですので安価といえますが、お墓に納骨されている人数分が必要です。納骨者が多いときはそれだけ費用がかさむ可能性があります。
新しいお墓の選択肢とかかる費用

近年では、さまざまな納骨方法があり、費用も方法により大きく異なります。ここでは、納骨方法と概算費用をご紹介します。自分に一番合った新しいお墓選びの参考にしてみてください。
一般墓所
一般墓とは、お寺や墓地にある一角の土地を借りて墓を立てる、もっとも一般的な「お墓」のことです。一般墓でかかる費用は主に以下の3点です。
| ①永代使用料 |
|---|
| 永代使用料とは、一角の土地にお墓を立てる権利を取得する、いわば「礼金」のようなものです。相場は60万円〜80万円程度とされていますが、立地や広さにより異なります。 |
| ②管理費 |
| 管理費とは、土地を利用する権利を維持する、いわば「家賃」のようなものです。年払いが一般的で1万円前後に設定されていることがほとんどです。なお、永代利用料や管理費は、霊園の運営者が公営であれば安価に、民間であれば高額に設定されていることが一般的です。 |
| ③墓石をたてる費用 |
| 墓石も新調するときには費用がかかります。石質・規模・デザインによって数十万円から、高額なものでは1,000万円を超えるものも珍しくありません。 |
移設先が一般墓であるときは、おおむね200万円程度の費用がかかります。パンフレットやチラシでアタリをつけることも重要ですが、事前に現地を確認したり、石材をチェックしたりすれば、失敗のない墓じまいができるでしょう。
また、年間かかる管理費も長期になれば高額になります。自分の状況や子どもたちの負担も踏まえてご検討ください。
永代供養墓
永代供養墓とは、一般墓と異なり「自分に代わって霊園や墓地の管理者がお墓や遺骨の供養や管理をする」という新しいスタイルのお墓です。自分でお墓を持ちたくない、経済的な負担を減らしたい、子孫にお墓の負担を残したくない、このように考える人にはおすすめの選択肢といえます。
「永代」と名前がついているため永久に供養してくれると思いがちですが、一般的には33回忌までと期間が定められていることがほとんどです。期間が過ぎると合祀される点に注意しましょう。
永代供養墓にはさまざまな種類があり、種類によって性質や金額が大きく異なります。これより解説しますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
個人(個別)墓
見た目は普通のお墓と何も変わらないタイプのお墓です。他人と同じお墓を望まない人にはおすすめの永代供養方法といえるでしょう。
ただし、供養方法や維持管理の方法が変わるものの、お墓を立てるという意味では一般墓のそれと変わりはありません。費用は150万円から200万円程度がかかるでしょう。
集合墓
集合墓とは、墓石は一つですが納骨スペースは分かれているタイプの永代供養墓です。墓石が不要であるため費用は個人墓よりも安価に設定されており、相場は約50万円程度です。
合祀墓
合祀墓とは、さまざまな人の遺骨を一か所に集める埋葬方法です。合祀墓は永代供養墓でももっとも安価で、約30万円程度で納骨が可能です。
樹木葬
樹木葬とは、墓石ではなく樹木の下に納骨するお墓の種類のことです。一般墓でも永代供養墓でも選択することが可能であり、自然回帰という考え方からも昨今人気が高まっています。
樹木葬は、個別出納骨するときは約100万円程度、合祀型の樹木葬であれば20万円程度の費用を目安にするとよいでしょう。
納骨堂
納骨堂とは、遺骨を一定期間保管するスペースを借りる仕組みのことです。納骨堂はあくまでも一定期間場所を貸しているだけですので、原則として管理や供養はしてくれません。そのほか、期間満了後は合祀することが前提でした。しかし、最近では永代供養を前提とした納骨堂も存在していますので、納骨堂に事前に確認しておくのがよいでしょう。
一言に納骨堂といってもさまざまなタイプがあり、費用も大きく変わります。
納骨堂の種類と費用イメージは以下のとおりです。
| 種類 | 概要 | 費用 |
|---|---|---|
| 自動搬送式納骨堂 | 立体駐車場のように、遺骨が参拝場所に自動的に運ばれてくる。 | 100万円前後 |
| ロッカー式納骨堂 | コインロッカーのように、指定の場所に遺骨を収めるタイプの納骨堂。 | 60万円前後 |
| 仏壇(霊廟)式納骨堂 | 文字通り仏壇が並んだ納骨堂。お花や供え物ができる点がメリット。 | 100万円前後 |
| 墓石式納骨堂 | 墓石をたてるタイプの納骨堂。室内に設置するため天気に左右されずに参拝できる。 | 100万円前後 |
散骨
散骨とは、火葬後の遺骨を粉末状にして、海・山・川など自然の中に撒き、自然に還す葬送方法です。お墓が不要であるため維持管理への負担がないほか、自然の中で故人を送るという考え方で、最近では宇宙に散骨する壮大なものも存在しています。
散骨費用は数万円から50万円程度とかなり幅があることが特徴です。海洋散骨が主流であることを前提にすれば、専用のクルーズ船をチャーターして家族や友人で散骨すると高額になりますが、専門業者に一括して依頼すると安価で散骨が可能です。
なお、散骨は法律・宗教感・遺族の気持ちなど、さまざまな面に注意と配慮が求められます。自治体や専門家へ情報収集を行い、家族や親族とよく話し合い、事後のトラブルを防止しましょう。
手元供養
手元供養とは、故人の遺骨の一部を形見の品と一緒に自宅などに保管する、いわばもっとも身近に故人を偲ぶことができる供養の方法です。維持管理費もかからないメリットのほか、故人といつまでも一緒にいたいと考える人にはおすすめの供養です。
手元供養に要する費用はおおむね10万円前後です。遺骨を細かく砕く「粉骨」にかかる費用が2〜3万円程度、残りの遺骨は一般的に散骨することが多いため、散骨に要する費用が数万円かかります。
墓じまいを進める上で後悔しないためのポイント
墓じまいにはさまざまなメリットもありますが、先祖代々のお墓を動かすためやり直しのきかない大事な決断であることも事実です。後悔しないためにはどのような点に注意すべきなのか、そのポイントを探ります。
急がずにゆっくりと考える
墓じまいは一度決断・実行すると元に戻せません。家族や親族でじっくり話し合いを重ね、納得がいくまで考えましょう。
特に、お墓に対する個人間の考え方の違いにも着目し、手続きや費用論に終始することは避けるべきでしょう。ご先祖様への感謝の気持ちを持って、慎重に決断するようにしてください。
さまざまな選択肢を考える
墓じまいは、古いお墓をなくすことではありません。従来の墓地や霊園への改葬だけでなく、樹木葬・散骨・手元供養など、さまざまな方法があります。
ご家族の価値観やライフスタイルに合った方法を見つけるためにも、先入観にとらわれることなく多くの選択肢を検討することが重要です。
行政書士や霊園の相談員などに聞いて決める
墓じまいのようなセンシティブで、かつ人生で何度も経験しないことを選択するときは、専門家や経験者の意見を聞くことも有効です。
葬儀社・霊園の担当者・行政書士など、それぞれの専門家がご家族の状況やご予算に合わせた最適なプランや方法を提案してくれます。実際に霊園を訪れ、目で見て、触れて、ご自身に合った供養の形を見つけることも可能です。
専門家の意見と自分の感性をもって決定すると、後悔のない墓じまいができるでしょう。
墓じまいで起こりやすいトラブルの実例と解決策

ご先祖様への感謝を込めて行う墓じまい。しかし、実際の手続きは複雑であるためさまざまな問題に直面することも珍しくありません。
親族との意見の食い違い、石材店とのトラブル、墓じまい先の選定など、多くの局面で悩まれる人も多いのではないでしょうか。ここでは、墓じまいをスムーズに進めるために、よくあるトラブルとその解決策を詳しく解説します。
親族と発生しがちなトラブル
親族間で発生するトラブルとして考えられるのは、意見が対立してしまうことです。なぜなら、故人への想いや今後の供養やお墓の維持管理に関する考え方の違いがあるからです。特に、費用負担や納骨先など強引に進めてしまうと、親族同士で大きな溝ができてしまうことにも繋がりかねません。
例えば、費用負担については、「私は費用負担できない」「費用負担の基準がない」といった意見が出ることがあります。また、納骨先については、「故人の希望を尊重したい」「自分が参拝しやすい場所を選びたい」など、さまざまな意見が噴出することが予想されます。
これらのトラブルを回避するためには、早い段階から家族で話し合い、それぞれの意見を尊重することが大切です。同様に理解すべきところは理解し、譲歩できる部分を模索することも必要でしょう。
そのほか、第三者に介入してもらうことも有効な手段です。弁護士・行政書士・僧侶などの専門家に立ち会ってもらうことで、客観的なアドバイスを得ることができ、問題が解決に向けて進む可能性があります。
石材店と発生しがちなトラブル
墓じまいは専門的な知識が必要なため、石材店に依頼することが一般的です。しかし、費用や工事内容にトラブルが起こるケースもあります。
費用面では、追加工事や材料費の変更などが発生し、見積提示額よりも高額になるケースがあります。そのほか、工事内容では工事の遅延や仕上がりが思っていたものと異なる、といったトラブルも起こりえるでしょう。
このようなトラブルを避けるためには、複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討することが重要です。また、契約書の内容をしっかりと確認し、不明な点は必ず質問するようにしましょう。さらに、工事の進捗状況を定期的に確認し、問題があればすぐに業者に連絡することが大切です。
石材店を選ぶ際は、実績が豊富で、評判の良い信頼できる業者を選ぶようにしましょう。また、アフターサービスについてもしっかりと確認すればトラブルの抑制に繋がります。
墓じまい先(納骨先)と発生しがちなトラブル
新しい納骨先とのトラブルも忘れてはいけません。なぜなら、墓じまいも契約であるため、見落としや誤解が発生してしまうからです。
納骨先との契約で注意すべきは、費用・手続き・メンテナンスに関するトラブルです。費用面では、当初の説明になかった金額を請求されることがあります。また、契約手続きでは想定していなかった書類の提出を求められることもあるでしょう。そのほか、メンテナンスの計画や付帯サービスなども気になるところです。
これらのトラブルは確認につぐ確認で解決するしかありません。
費用面では、総額と内訳をつぶさに確認し、追加費用の可能性がある項目を事前に理解すれば防止することができます。契約後に施設利用料が増額になることもありますので、連絡事項やホームページのお知らせは適宜チェックすることも必要でしょう。
また、契約手続きにおいては、流れ・スケジュール・必要書類・受入可能な国籍や宗派などを事前に把握しておくことが求められます。
管理人の常駐・メンテナンス履歴や計画などは事前に確認しておけば墓じまい後も安心です。また、付帯サービス(会議室が使えるかどうか・法要施設の種類や利用料・飾りや供物の料金・バス送迎など)は霊園選びでは特に重要です。実際に現地でスタッフから説明を受けることで、内容やホスピタリティをチェックすることができ、トラブルを回避できるでしょう。
墓じまいをするかどうかは、慎重に考えて決めよう
故人の眠るお墓は家族にとって大切な場所です。
墓じまいは、お墓の管理負担からの解放といったメリットと、故人とのつながりを断ち切るように感じてしまうといったデメリットがあります。これらを天秤にかけ、法律や宗教的な側面も考慮しながら、家族でよく話し合い、専門家のアドバイスも得て慎重に進めることが重要です。
また、冒頭でお話したように、墓じまいは終活の一部ともいえます。そのため「墓じまいをしない」という選択肢も間違いではありません。それ以外にすべき終活、例えば所有する不動産などの財産を整理したり、子どもに負担をかけない設備のある住宅に移転したりすることでも、子孫の負担を軽減させることができます。
ご家族の状況や考え方は十人十色です。墓じまいは、自分だけでなくご家族皆が納得できるよう、じっくり話し合い、後悔のない選択をしてください。