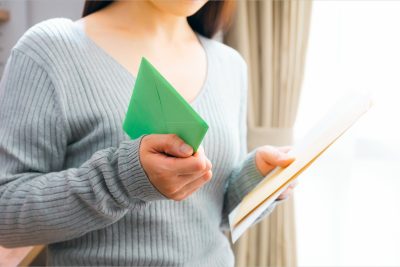賃貸物件を探す際、気になるポイントのひとつが「湿気」です。過度な湿気はカビや結露などのトラブルを招きますが、湿度対策を部屋探しの段階で対策検討するのは現実的ではありません。
そこで今回は、梅雨前にできる湿度対策と、湿度対策を考えた部屋探しのポイントについて解説していきますので、お困りの方はぜひチェックしてみてください。
部屋の湿気がひどい原因

湿気とは、空気中に含まれている水分割合のことを指します。根本的な原因として、日本はそもそも湿度が高い気候です。しかし、物件や部屋の構造、その利用方法によっても湿度がより高くなることも珍しくありません。
こまめな換気をしていない
昨今の建築技術の向上は素晴らしく、夏は涼しく冬は暖かい物件が増えてきています。気密性が高いために快適に過ごすことができる一方、湿気も室内に閉じ込められるため、湿度が高くなることが考えられます。
部屋干しをしている
室内に洗濯物を干していると、洗濯物から発生する湿気が湿度を押し上げていることが考えられます。脱水後の洗濯物に含まれる水分は、乾燥時の洗濯物重量の約60%程度、成人一人が一日に洗濯する量は約1.5㎏とされています。
洗濯物が乾くということは、洗濯物に含まれている水分が室内に放出されることと同義です。1.5㎏×60%で計算すると、約900㎖の水分が室内に放出されることになります。
出典:平成22年度日本建築学会 近畿支部研究発表会 「実測に基づく室内干し時における洗濯物の乾燥時間および室内温湿度環境」
観葉植物を部屋に置いている
多くの植物は、「蒸散」と呼ばれる植物の体内に存在する水分を空気中に排出する活動を行います。観葉植物の有無における部屋の湿度の差は、日中で最大約20%発生するという研究結果があります。
観葉植物の種類にもよりますが、観葉植物の設置と湿度には極めて密接な関係があるといえるでしょう。
出典:日本建築学会計画系論文集 第464号,39 −46,1994年10月「観葉植物が室内の温熱環境および温熱快適性に及ぼす影響」
湿気調節ができない素材を用している
日本の建物は、古くから湿度の調整が自動的にできる建材を利用してきた歴史があります。しかし、最近の建物は建築コストや維持補修の利便性を優先し、湿度の調整機能に乏しい資材を利用するようになっていきました。
和室に利用される畳や漆喰の壁などは調湿資材として有名です。フローリングでも、無垢材であれば木材本来の調湿機能が働き水分を吸ってくれますが、複合フローリングの場合、ワックスの塗布によりその機能は働かなくなります。
部屋の湿気がひどいと引き起こすかもしれない健康被害

室内における適正な湿度は、40~70%が適正であるとされています。湿度が低いとウイルスの繁殖を招くおそれがある一方、湿度が高いとカビやダニの発生が促進されるため、適切な湿度を保たなければなりません。
多湿の部屋で長く生活していると、知らず知らずのうちに発生したカビを吸い込んでしまい、アレルギーや中毒、感染症などを引き起こすことがわかっています。たとえば、鼻炎や肺炎、水虫などが挙げられます。
部屋の湿気がひどいときに試したい改善法
部屋の湿気がひどい場合、どのような対策を行えば改善できるのでしょうか。ここからは、比較的簡単にできる湿気対策の方法を紹介していきます。
部屋内にこもった空気の換気を行う
部屋にこもった空気を入れ替えるために、在室時には窓を開けて換気を行いましょう。換気を行う際は、1つの窓を開けるのではなく、空気の入口と出口を作り、空気が部屋全体を通る道を作ることが重要です。これによって除湿効果が上がるほか、短時間で空気を入れ替えることも可能です。
もし窓が1つしかない場合は、扇風機を利用するなどして、風の通り道を確保するという方法もあります。
出典:東京都福祉保健局 「住まいの健康配慮ガイドライン」
除湿器やエアコンの除湿機能を活用する
窓を開けるのが困難な場合、除湿器やエアコンの除湿機能によって湿度を下げる方法があります。除湿器を利用する際には、部屋のドアを閉めておくことでより除湿効果が高まります。また、リビングや寝室などの広い部屋を除湿する場合は、扇風機などを併用し、空気を循環させながら除湿することを意識しましょう。
洗濯物を外に干すようにする
洗濯物を室内干しする場合は、どうしても湿度が高くなってしまいます。天気の良い日などは、洗濯物を外に干すだけでも、湿気の改善は十分に実感できるでしょう。
しかし、マンションの1階部分などの低層階や、日当たりが悪い部屋の場合は、洗濯物を外に干すことが好ましくないケースも少なくありません。やむを得ず洗濯物を部屋干しする場合、先述した除湿器やエアコンの活用がおすすめです。
部屋干しにあたっては、可能な限り部屋の中心部分に洗濯物を設置するよう心がけてください。このとき、除湿器を洗濯物の真下に設置するとより効果が上がります。
除湿器に近いところに厚手のものを、遠いところに薄手のものを設置すれば、比較的短時間で乾燥させることができます。
家具の配置を変える
湿気はお部屋の上部ではなく下部に溜まります。また、家具を隙間なく配置していると空気が循環せず、湿気が溜まりやすくなります。掃除の際にも手が届かなくなるなどして、衛生的にも決して良いとはいえません。
家具と壁の間を5cm程度空けるだけで空気が循環し、湿気が溜まりづらくなります。また、これから家具の購入を検討されている方は、設置場所や掃除の手間についてチェックし、今後の湿気対策に役立ててみてください。
賃貸物件を借りる際に意識したい!湿度がこもりにくい部屋の特徴

ここまで湿気対策を記載してきましたが、根本的に湿気がこもりやすい建物が存在していることも事実です。たとえば、日当たりが悪いお部屋や、低層階のお部屋などは湿気が溜まりやすいといえるでしょう。また、窓が一ヶ所しか設置されていないなど、空気の循環がスムーズでない建物などにも注意が必要です。
設備面においては、窓が複数方向に設置されていてもエアコンが設置されていない、もしくはエアコンが設置できない居室などがある場合も、入居後の湿気対策に苦労する可能性があります。間取りに関しては、脱衣スペースが独立していない(脱衣スペースと廊下の間に扉が設置されていない)お部屋などは、浴室や洗面所の湿気が居室および玄関に流れ込むことが多く、湿気対策が必要になることも珍しくありません。
部屋の構造を変えることはできないため、湿気対策の手間を少なくしたいと考えている方は、最上階の部屋や角部屋など湿気が溜まりづらい部屋に住んでみてはいかがでしょうか。
部屋の湿度を適切に保って快適な生活を!
湿度は適切な状態に保つことに意味があり、高すぎても低すぎても百害あって一利なしです。重要なのは、こまめに窓を開けて換気を行うなど、日々の湿気対策を怠らないことです。
部屋や物件によって、湿気の発生原因はそれぞれ異なりますが、原因に合わせて適切に対応すれば比較的簡単に対処できます。自分なりの湿気対策を実践し、日々の生活をより快適なものにしましょう。