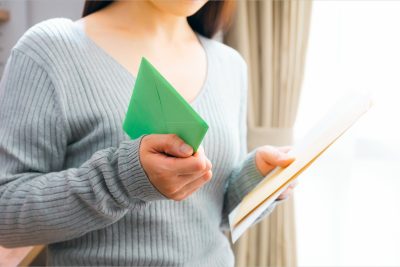お部屋探しをしていると、「契約期間2年」「普通借家契約」という文字を目にすることがほとんどです。日本の賃貸物件の多くは、この「普通借家契約」という契約形態を採用しています。
実は、この普通借家契約には借主を強く保護する仕組みが数多く組み込まれています。なぜ日本の賃貸契約にはこのような特徴があるのでしょうか。
この記事では、普通借家契約の基本的な仕組みから、なぜ「2年契約」が多いのかという理由、そして契約の更新や途中解約をする際の注意点まで分かりやすく解説します。更新への不安を解消し、安心して納得のいくお部屋探しができるよう、ぜひ最後までお読みください。
普通借家契約とは?
最初に、賃貸契約の基本となる「普通借家契約」がどのようなものなのか、その特徴を見ていきましょう。
普通借家契約と定期借家契約の違い
賃貸借契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。この2つの最大の違いは「契約更新の有無」です。2種類の契約の違いを表にまとめました。
【普通借家契約と定期借家契約の違い】
| 項目 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |
|---|---|---|
| 契約の更新 | 更新は原則可能 | 更新という概念がない期間満了で契約は終了する |
| 再契約 | 更新のみ | 借主・貸主双方の合意によって再契約は可能 |
| 契約期間 | 1年以上で設定期間の定めがない契約も可能 | 自由に設定できる(1年未満という契約も可能) |
| 途中解約 | 可能 | 原則、借主・貸主双方からの途中解約は不可能 |
| 貸主からの解約・更新拒絶 | 「正当事由」がなければ解約や更新拒絶はできない | 契約期間満了時に、貸主の自由意思で再契約しないこともできる |
このように、普通借家契約は家賃の滞納や素行不良などの問題がない限り、借主が望む限り住み続けられる可能性が高い、借主保護の考え方が強い契約です。日本で流通している賃貸物件の大多数が、この普通借家契約を採用しています。
契約期間の意味や意義
普通借家契約では、契約期間を「2年」と定めるのが一般的ですが、まれに「期間の定めがない」契約も存在します。そもそも、この契約期間にはどのような意味があるのでしょうか。
それは貸主と借主、双方の契約条件を明確にするためです。契約期間を定めることで、その期間内の家賃やルールが固定され、お互いに安定した契約関係を築くことができます。もし期間の定めがないと、貸主からの解約申し入れのハードルが少し下がるなど、借主にとって不安定な要素が生まれる可能性もゼロではありません。
「2年」という期間を定めて契約を更新していく「合意更新」の形が、お互いの権利や義務を定期的に確認しあえるため、双方にとってメリットが多いことから、一般的な形となっているのです。
普通借家契約に2年契約が多い理由
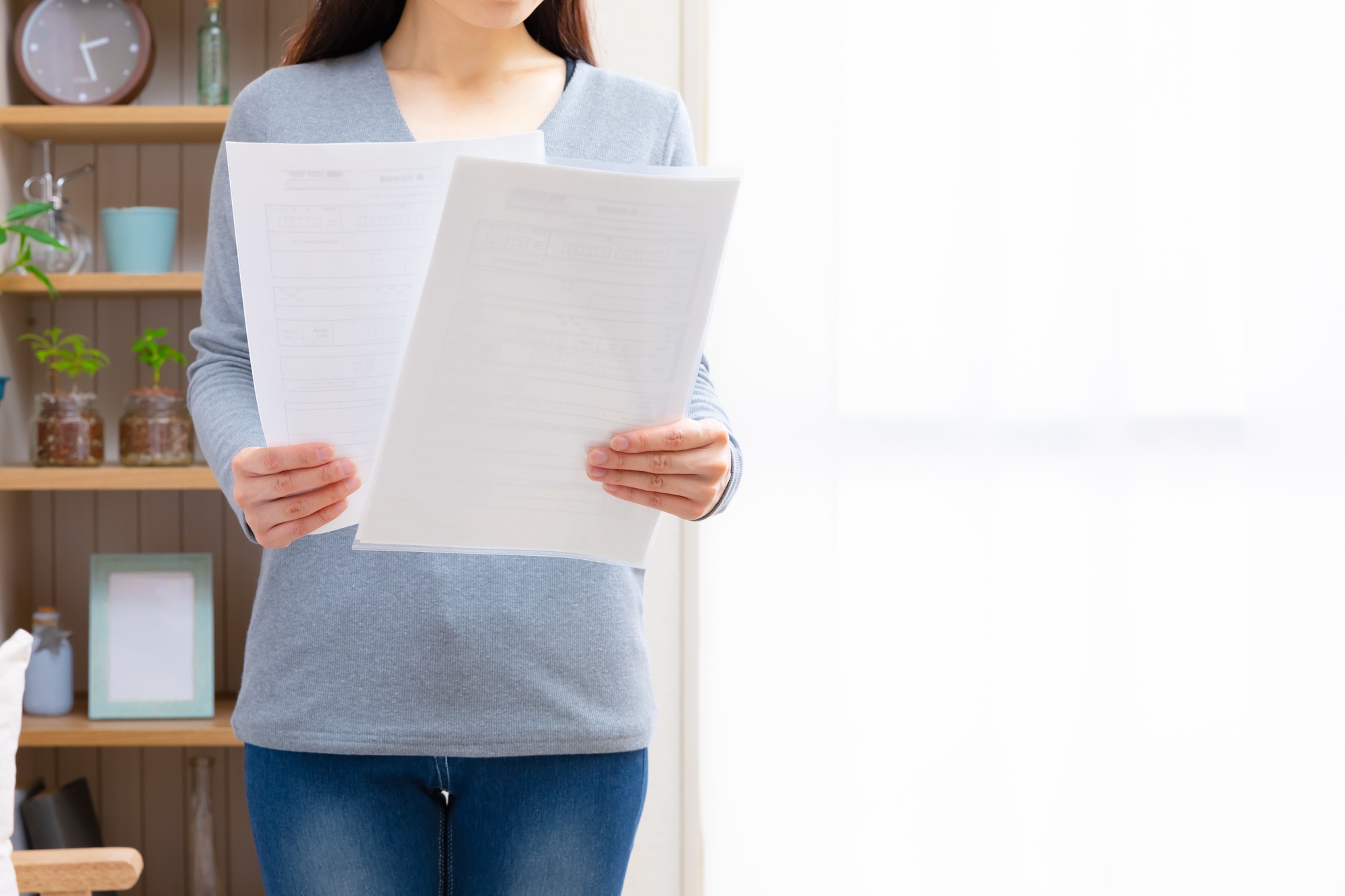
では、なぜその契約期間が「2年」なのでしょうか。法律で定められているわけでもないのに、ほとんどの物件が2年契約なのには、いくつかの理由があります。
普通借家契約のルーツを辿ると、戦時中に作られた「旧借家法」という法律に行き着きます。国のために戦地へ向かった兵士たちが、その間に家族が家を追い出されたり、命からがら帰ってきたときに自分自身の家がなくなったりすることを防ぐことが、この法律の重要な使命でした。
「住む人の生活である家を安易に奪ってはならない」という当時の想いが込められた借主保護の精神は、時代を超えて現代の法律にも息づいており、今日の私たちの暮らしの安心に繋がっています。
ここからは、そんな普通借家契約に2年契約が多い理由をみていきましょう。
業界の慣習的なもの
実は、「2年」という期間に法律上の特別な意味は存在しません。これは長年の業界の慣習によるところが大きいのです。
貸主と借主、双方の視点から考えてみると、1年契約では借主にとって更新手続きや更新料の支払いが毎年発生して面倒である一方、貸主にとっても入退去が頻繁になり安定した経営が難しくなります。逆に3年や5年契約では、借主は転勤やライフスタイルの変化に対応しにくく期間が長すぎると感じる一方で、貸主もその間の家賃改定などがしにくくなってしまいます。
このように、「1年では短すぎるし、3年以上では長すぎる」という双方の心理的なバランスから、「とりあえず2年」という期間が、手頃で合理的な年数として定着した、と考えるのが自然でしょう。
更新料の支払タイミングからみた落としどころ
もう一つの視点が、「更新料」の存在です。更新料は、契約を更新する際に借主が貸主へ支払うお金で、家賃の1ヶ月分程度が相場とされています。
貸主側のビジネス視点で見ると、この2年ごとの更新料は、安定した事業を継続するための重要な収入源の一つです。また、多くの物件では、1年や2年未満といった短期間で解約した場合に「短期解約違約金」が設定されています。
これらの仕組みを考えると、「2年」という期間は、貸主側が初期投資(リフォーム費用など)を回収しつつ事業を成り立たせるための、そして借主側も違約金を払うことなく住み替えを検討できる「ほどよい期間」として、日本の賃貸市場に根付いたという側面もあります。
普通借家を更新する際のポイント
契約期間の満了が近づくと、管理会社や貸主から更新に関するお知らせが届きます。慌てずスムーズに手続きを進めるために、事前に確認しておきたいポイントを解説します。
更新方法を確認する
まずは、更新の手続きがどのように進められるのかを確認しましょう。通常、契約期間が満了する1~3ヶ月前に「契約更新のご案内」といった書類が郵送などで届きます。その案内には、おおむね以下のようなことが記載されています。
・更新の意思表示をいつまでにするか
・どのような書類(更新契約書、身分証明書のコピーなど)が必要か
・更新料などの費用をいつまでに支払うか
・新契約期間の契約条件はどのようなものか
内容をよく確認し、不明な点があれば早めに管理会社へ問い合わせましょう。
契約更新と再契約の違いを確認する
前述の通り、普通借家契約は「更新」であり、定期借家契約の「再契約」とは意味合いが異なります。
・更新(普通借家契約)
これまでの契約内容を基本的に引き継いで、期間を延長すること。
・再契約(定期借家契約)
これまでの契約を一度完全に終了させ、新たに契約を結び直すこと。
普通借家契約の更新では、家賃の大幅な値上げなど一方的に不利な条件変更をされる心配はほとんどありません。仮に大幅な値上げを要求されても、家賃値上げは双方の合意が前提となっているため、借主側で断ることができます。
一方、定期借家契約を再契約する際には状況が異なります。仲介手数料の支払いが必要になったり、礼金の再度の支払いを求められたり、家賃が変更されたりする可能性があります。定期借家契約では、貸主が提示する条件を受け入れなければ再契約ができないため、借主には交渉の余地がほとんど残されていません。
こうした違いを見ても、普通借家契約が借主により有利な制度として設計されていることが明らかです。
更新にかかる費用などは規約を確認する
更新時に気になるのが、やはり費用の問題です。案内が届いたら、お手元の賃貸借契約書と見比べて、以下の点を確認しましょう。
・更新料の金額は契約書に記載の通りか?
※例:新家賃の1ヶ月分など
・更新事務手数料(更新手続きを行う不動産会社へ支払う手数料)はかかるか?
※更新料とは別にかかるケースがあります
・火災保険料や保証会社の更新料が必要か?
これらの費用を支払わなかった場合、契約を守る意思がないと見なされ、契約解除の正当な理由と判断されてしまう可能性もあるため、必ず期限内に支払いましょう。
また、法人契約の場合は、これらの費用を会社が負担してくれるのか、個人で負担するのかも、会社の規定を事前に確認しておくと安心です。
更新を拒絶される可能性はある?
「住み続けたいのに、大家さんから更新を断られることはあるの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、ご安心ください。普通借家契約では、貸主側から更新を拒絶するには「正当事由」が必要だと法律で定められています。
正当事由とは非常に限定的なケースに限られており、具体的には家賃を長期間滞納している場合、ペット不可物件で無断でペットを飼育しているなどの重大な契約違反がある場合、騒音などで他の入居者に著しい迷惑をかけている場合、そして家主自身が居住する必要があるなど、やむを得ない事情がある場合が該当します。
つまり、ルールを守って普通に暮らしている限り、一方的に更新を拒絶されて住まいを追われる心配はほとんどないと考えていいでしょう。
普通借家を2年未満で解約したいときの注意点

転勤や転職、結婚など、ライフステージの変化によって2年の契約期間を満了する前に解約(途中解約)したくなるときやしなければならないときもあります。そんな時に注意すべき点を確認しておきましょう。
短期解約違約金が発生することがある
賃貸契約では、「契約開始から1年(または2年)未満に解約する場合には、家賃の〇ヶ月分の違約金を支払う」という趣旨の「短期解約違約金」に関する特約が盛り込まれていることがあります。
これは、家主が早期の退去によって被る損失(次の入居者のためのリフォーム費用など)を補填するためのものです。2年未満で引っ越す可能性がある場合は、契約時にこの特約の有無と内容を確認しておきましょう。
比較的短期の解約となるため、故意過失による借主負担の原状回復が高額化する
退去時には、借主がわざとつけたり、不注意で壊したりしてしまった傷や汚れを元に戻す「原状回復」の義務があります。この費用は、住んでいた年数に応じて「減価償却」が考慮されます。
例えば、壁紙は6年で価値が1円になるとされています。長く住むほど、経年劣化による価値の減少が考慮されるため、借主の負担は軽くなります。しかし、入居後1年など短期間で退去する場合、この減価償却があまり進んでいないため、もし壁紙に大きな傷をつけてしまった場合などの修繕費用の負担割合が、相対的に大きくなる傾向があるのです。
普通借家で物件を探している人におすすめの物件条件
これから普通借家契約でお部屋を探すという方に、長く快適に暮らすために、契約前にチェックしておきたいおすすめの物件条件をご紹介します。
更新料に問題がない物件
長く住むことを考えると、2年ごとに発生する更新時の費用は、家計に影響を与えるポイントです。契約書に記載されている更新料の金額が、自分の経済状況にとって無理のない範囲かを確認しましょう。
負担に感じる人もいるかもしれませんが、そんな時は「更新料無料」の物件に注目するのがおすすめです。初期費用だけでなく、数年後を見越したトータルコストで考えると、非常にお得な選択肢と言えるでしょう。賢く物件を選んで、将来の負担を軽くするのも一つの手です。
短期解約違約金の有無
「今は長く住むつもりだけど、将来どうなるか分からない…」という人は、短期解約違約金の有無をチェックしておきましょう。
特に転勤の可能性がある人や、近い将来に実家に戻る、結婚するなどのライフプランを考えている人は、万が一の場合に備えて、違約金がない物件や、条件が比較的緩やかな物件を選ぶと安心です。
なお、法人契約では、短期解約違約金の設定について社内規定が設けられていることも珍しくありません。こういった詳細の規定については、なかなか社員で把握することは困難ですので、不動産会社に規定を伝え、規定に合致した物件を探してもらうか、もしくは条件交渉をしてもらう方法で物件を探すのが良いでしょう。
解約予告期間もチェック
中途解約する際に、もう一つ重要なのが「解約予告期間」です。これは、「退去します」と伝えてから、実際に契約が終了するまでの期間のことで、一般的には「1ヶ月前」と定められているケースがほとんどです。
これが「2ヶ月前」など、一般的な期間より長く設定されている場合は少し注意が必要です。なぜなら、退去を決めてから家賃を余分に支払う期間が長くなってしまうためです。
また、退去月の家賃の精算方法も「日割り」「月割り」など物件によってさまざまです。契約書で事前に確認しておきましょう。
普通借家契約は2年か3年が基本!更新の際も慌てず対応しよう
今回は、「普通借家契約」の基本から、多くの人が疑問に思う「2年契約」の理由、そして更新・解約時の注意点までを解説しました。
普通借家契約は借主の権利を守る、更新を原則とした契約です。そして「2年契約」は法律ではなく、貸主と借主双方にとって都合の良い慣習として定着したもの。だからこそ、更新時の「更新料」や短期解約時の「違約金」といったルールは、契約書で事前に必ず確認しましょう。月々の家賃だけでなく、更新料の有無などトータルコストで判断する視点も大切です。
また、少し面倒に感じる契約更新ですが、これには家主さんや管理会社が緊急連絡先などをアップデートする、という重要な意味も含まれています。万が一の災害やトラブル時に迅速な連絡が取れることは、自分や家族の安全を守る上で欠かせません。
更新は、安心して暮らすための必要な作業と捉え、急な更新の連絡にも慌てることのないよう、契約時に更新について確認しておくと良いでしょう。